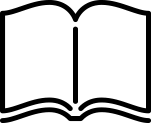ソーイングテーブルとは主に裁縫をするための作業台として作られたテーブルのことで、快適な作業ができるよう裁縫に特化した機能が多数付いています。
長い歴史の中でさまざまなスタイルのソーイングテーブルが生み出されてきましたが、その美しい見た目や機能性の高さは現代でも評価され、多くの人に愛され続けています。
ソーイングテーブルの特徴
作業がしやすい天板

長い布を広げてもできる限りぶら下がらないよう、また快適に効率良く作業ができるよう、天板には広く平らなスペースが設けられていることが多いです 。
さらに針などの小さな備品の落下を防ぐため、天板の周りを縁取るように少し立ち上げて作られているものもあります。
収納力に長けている

裁縫に必要なたくさんの備品をしまうため、天板の下には引き出し式、もしくは天板がフタのようになるボックス式の収納スペースが備え付けられています。
小さな備品を分かりやすく区別してしまえるよう引き出しの内部が細かく仕切られていたり、ボックス式の場合天板の裏面に収納ポケットやピンクッションが付いていたりと、快適に作業するための工夫がたくさん見られます。

中でも特徴的なのが、毛糸などをしまう目的で作られた布袋またはラタン製のバスケットが付いたデザインで、一般的なテーブルでは見られないソーイングテーブル特有のデザインとして現代でも人気を博しています。
便利な機能が付いたソーイングテーブルの種類
手軽に移動できるタイプ

ちょっとした作業をする時に便利な小振りのもの、また脚にキャスターが付いたものなどは、移動性や携帯性に特化しています。
天板を拡張できるタイプ

作業をしない時にはコンパクトに使用し、作業時にパッと天板を拡張できるドロップリーフテーブルのようなタイプもよく見られます。
高さを調節できるタイプ

作業がしやすい50〜65cmくらいの高さで設計されていることが多いですが、立ち作業と座り作業のどちらにも合わせられるよう高さを調節できる機能が備わったものもあります。
ソーイングテーブルの歴史

ソーイングテーブルの起源は1770年頃まで遡ります。当時イギリスの裕福な家庭で、貴婦人たちが裁縫や余暇を楽しむためのテーブルとして作られたのが始まりと言われており、女性でも扱いやすいよう軽量かつ繊細に作られました。
そして1780年代になると、独立戦争後のアメリカでもソーイングテーブルを取り入れるようになっていきます。アメリカでは主にマホガニー材が用いられ、細いラインで垂直かつシンプルなデザインが印象的なシェラトン様式や、重厚で華麗なデザインが特徴のエンパイア様式で作られることがほとんどでした。ヨーロッパでもゴシック様式やロココ様式などその時代に合わせた様々なスタイルのソーイングテーブルが生み出されていきます。

デザイン面だけでなく機能面も多種多様に優れ、引き出しが1つだけ付いたシンプルな構成のものもあれば、裁縫道具だけでなく文房具やボードゲーム盤などもしまえるようなキャビネット型のものもたくさん作られました。
1800年代初めにミシンが製品化されると、それまで個々の手作業で行っていた縫製は、産業革命という時代背景もあって工場の仕事へと移行するようになります。その後足踏み式ミシンが誕生するとミシン専用の作業台「ミシンテーブル」が普及していきました。
家庭内の万能な家具であるソーイングテーブルには、ミシン作業に特化したミシンテーブルとはまた異なる魅力があり、当時から変わらぬ人気を集めながら現代でもなお様々なデザインのソーイングテーブルが生まれ続けています。
「ミシンテーブル」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。
現代での使われ方

裁縫だけでなく、手紙を書いたり読書をしたりチェスを楽しんだり、古くから様々な用途で愛用されていたソーイングテーブル。
その機能性の高さは現代でも十分に活かすことができ、サイドテーブル・コーヒーテーブル・お化粧台など、アイディア次第で色々な活用法を楽しむことができます。
細々としたものをスッキリと収納できる上、普通のテーブルとは一風変わったデザイン、そして高級木材の美しい木目によってお部屋の中の目を惹く存在となり、インテリア性にも非常に優れた家具といえます。