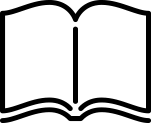衣桁とは、着物を掛けておくための家具のことです。いくつかの細い木材を組み合わせて作られており鳥居のような形が特徴的です。
衣桁の特徴

着物をたたまずに広げて掛けておけるのが衣桁の特徴です。細い木を鳥居のように組んだ形状は着物を掛けるのに便利な形というわけです。例えば、近日着る予定の着物を広げて掛けておけば、折りじわなどがきれいに取れますし、逆に着ていた着物を一時掛けして湿気などを逃すのにも重宝します。
素材・装飾など

衣桁は角柱か丸柱でつくられており、木材にニスや黒漆、朱漆が塗られていることが多い特徴があります。なかには蒔絵や装飾金具が施された豪華なデザインのものもあり、華やかな着物に見劣りしないデザインになっています。
衣桁の種類
大名衣桁

足元に土台の付いた衝立式の衣桁です。着物を折り曲げることなくかけることができるため、着物を一時置きしつつその色柄を楽しむこともできます。現在では、呉服店などで着物の展示に使われることが多くなっています。
屏風式の衣桁

中心で折りたためる形をした衣桁です。L字に変形できるので部屋の隅に置くことも可能。使わないときは畳んでコンパクトにできるため一般の家庭にも置きやすい形になっています。
衣桁の歴史

衣桁の歴史は非常に古く、平安時代には登場していました。当時から形状はほとんど変わっていませんが、御衣懸、衣架と呼ばれていたようです。室町時代の末頃から衣桁と呼ばれるようになりました。
実用的に着物を掛ける意味合いだけでなく、装飾の乏しい部屋のインテリアとしての役割ももっていました。また、晴れの日は美しい着物を掛けて装飾の一部としても使われたようです。
江戸の中期に屏風式の衣桁が誕生し、そこから明治にかけては屏風式の衣桁が主流になっていきます。
着物を着る機会が減った近年では衣桁を持つ家庭はかなり減っており、その姿は呉服店や婚礼衣装などの展示場、旅館などで見ることができます。
衣桁と衣紋掛けの違い

着物を掛けるものには、衣桁以外に衣紋掛けというものもありますよね。この2つの違いは何なのでしょうか。
衣桁はあくまで着物を掛けるための家具です。簡単に言うと、着物専用の物干しざおのようなものと考えれば分かりやすいでしょう。これに対し衣紋掛けはハンガーの役割を持っています。通常のハンガーと比較すると横棒の長さがあり、着物の袖までしっかりと通せるつくりになっています。