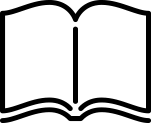ペーパーコードとは、その名の通り「紙の紐」のことですが、ただの紙ではなく樹脂を含ませてより合わせた紙紐のことを指します。
主に椅子の座面などに使われます。
ペーパーコードを使った椅子は、骨格となる木製のフレームに1脚あたり約120mの長さのペーパーコードを、職人の手作業で編み込んでいくことで出来上がります。
北欧インテリアでよく見かける家具ですが、近年では日本でも多くつくり出されています。
シンプルで美しく、機能性の高いペーパーコードチェアは、時代を超えて今も世界中で愛され続けています。
ペーパーコードの特徴
美しいデザイン
異なる素材で構成されたペーパーコードチェアは、木材のみでつくられた椅子にはない、独特の魅力があります。
思わず触ってみたくなるような質感や丁寧に編み込まれた座面からは手仕事ならではの温もりが感じられ、繊細かつ柔らかな雰囲気を醸し出します。
骨格となるフレームの素材や形、ペーパーコードの編み方によってデザインや印象も変わってくるので、色々と見比べてみるのも楽しいですね。

高い耐久性
「素材が紙」と聞くとすぐに破けたり切れたりするのでは?と心配になりますよね。
ペーパーコードの原料は、強度のある繊維の長い天然パルプを使用していることが多く、その頑丈な紙を3本より合わせて使われるため耐久性に優れています。その丈夫さは革や布張りと同等か、もしくはそれ以上の場合もあります。
紙は品質に差が出ることもなく、質も見た目も均一に仕上げることができるのも特徴の1つです。

快適な使い心地
素材が紙のため程よいクッション性があり、座った瞬間優しく受け止めてくれるような感覚を味わえます。
そして、はじめはピンと固く張ったペーパーコードも、使い込んでいくうちに体にフィットするように変形していくところに大きな特徴を持ちます。
徐々に馴染んでいく感覚に愛着が湧き、自分に合った座り心地を楽しめる所に最大の魅力を感じる人も多いはず。
また、使い心地が快適な理由は他にもあります。それは「通気性の良さ」と「軽さ」です。
ペーパーコードは編み込んで作られるため空気の抜け道があり通気性が抜群です。夏には熱を逃して蒸れることがなく、冬には暖房の暖かな空気を通して座面を冷やさないといったように、オールシーズン快適に過ごすことができます。
そして紙を素材としたペーパーコードは木材のみの椅子に比べると軽いです。日常で動かす機会の多い椅子が軽くて扱いやすいと嬉しいですよね。実用的な機能性と美しさを兼ね備えた優れた素材といえます。

お手入れしやすい
ペーパーコードは、1本1本樹脂でコーティングされているため水分をはじきます。
そのため、水分や汚れが付いた時には染み込む前にすぐに拭き取ることで、シミを残すことなく落とせます。
水気をしっかりと絞った布を使い優しく叩くことで拭き取ることもできますが、拭き取り後に濡れたままで使用するとペーパーコードが伸びたりカビの原因にもなったりするため、十分に乾かしてから使用するなど注意が必要です。
普段のお手入れも簡単で、気が付いた時に掃除機で隙間に入ったゴミやホコリを吸い取ったり、乾いた布ではたいたり、逆さにして座面の裏から軽く叩くだけでも綺麗になります。

ペーパーコードのお手入れについて、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。
ペーパーコードの種類
平編み
ペーパーコードチェアに用いられる座面の編み方は、大きく分けて2つあります。
まずは日本で通称「鹿の子編み」とも呼ばれる平編みからご紹介します。
こちらは、横方向に向かって表目と裏目を縦横交互に編んでいく技法です。
凹凸が多く出る編み方なので肌に触れる面積が狭く、サラッとした使用感で通気性の良さに優れています。
身近な使用例でいうと、ポロシャツやニットの編み方などが想像しやすいかもしれません。
次にご紹介する「封筒編み」よりもフラットでしっかりとした使い心地を感じる編み方です。

封筒編み
いわゆる手紙を入れる封筒の裏面のような形の編み方です。
平編みより難易度が高いといわれていて、一定の力加減を保ちながら、斜めのラインがまっすぐ揃うように編んでいくことがポイントとなります。
座面の中心部分に向かうほど張りが若干緩やかになるため、包み込むようなゆったりとした座り心地を味わえます。

ペーパーコードの歴史
元々は第一次世界大戦中に麦などの農作物をまとめる紐として使われていました。
しかし1940年代頃に「革などの素材よりも低コスト。優れた強度と耐久性。使い心地が快適。」といった理由から次第に椅子の座面へと転用されるようになります。
ペーパーコードの代表作には、北欧デザインの巨匠ハンス・J・ウェグナーの「Yチェア」「PP68」や、ボーエ・モーエンセンの「J39」などがあります。
中でも、背もたれや後脚が描く曲線美・封筒編みの座面が特徴的なYチェアは、日本での人気も非常に高いです。
軽くてシンプルなデザインでありながら、使う人の体に寄り添い優しい座り心地を与えてくれる世界的ロングセラー家具として有名です。
誕生から長い月日が経った今もペーパーコードは作られ続け、その技術は大切に受け継がれています。

張り替えのタイミング
長年使用しているとどうしてもコードがたるんできたり、切れてしまったり、汚れが目立ってきたりします。
そんな時はペーパーコードの張り替えをすることで、新品時のような張り感や質感を再び手に入れることができますよ。
張り替えの目安はおよそ10〜15年ほどですが、使い方や環境によっては20年近く持つこともあります。
耐久性のある素材だからこそ、じっくり時間をかけて自分の体に馴染ませていくという醍醐味を楽しみながら、少しでも長く愛用していきたいですね。

ペーパーコードとロイドルームの違い
ペーパーコードと似ている素材に「ロイドルーム」というものがあります。
パッと見ただけでは違いが分かりづらい2つですが、それぞれの共通点と相違点について見ていきましょう。
ロイドルームとはスチールワイヤーに紙を巻きつけた素材のことを指します。編地ならではの繊細で温かな雰囲気を持ちながら、フレームと別々に製造することで自由度の高いデザインを可能にしています。
両者の共通点は「素材に紙が使われているところ」と「木製家具のフレームに巻きつけながら編み上げていく製造方法」です。
異なる点は、ロイドルームにはスチールワイヤーが使用されているところです。スチールワイヤーには、水分などで錆びて折れることがないよう防水・防錆加工が施され、さらに巻きつける紙にも防水加工を施し、素材自体の耐久性・防水性を高めています。
そのためペーパーコードよりも湿気に強いといえます。また着色のしやすさからカラーバリエーションが豊富なところも特徴の1つです。


「ロイドルーム」について、以下でも解説しています。こちらもぜひご覧ください。