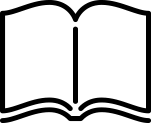栗とは、ブナ科クリ属の落葉広葉樹のことです。
北海道南部・本州・四国・九州とほぼ全都道府県に分布しており、温帯域を好んでいるため日当たりの良い山地や丘陵などに自生しています。そして古くから栽培も多く行われてきました。
国外ではアジアの広い範囲・北アメリカ・ヨーロッパなどにも分布します。
栗と聞けば秋の味覚代表である、あのイガのついた茶色い実を思い浮かべますよね。
しかし魅力はそれだけに収まらず、木材としてもとても優良なんです。
遡れば縄文時代から食用として木材として極めて重要とされてきた栗。
何千年もの間 途絶えることなく大切にされ続けてきた栗の特性や魅力はどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう!
栗の種類
クリ属の植物は12種類ありますが、その中で経済栽培されているのは「ニホングリ」「チュウゴクグリ」「ヨーロッパグリ」「アメリカグリ」の4種類です。
どの種類も食用として利用されていることは共通していますが、木材としては「ニホングリ」「アメリカグリ」が使用されることが多いです。しかし「アメリカグリ」は1904年に発生した焼き枯れ病(胴枯病)により大半が消滅状態になったため、市場ではほとんど流通していません。
それでは栗材として主に使用されている「ニホングリ」についてご紹介します。
ニホングリ
日本の広い地域で自生している「シバグリ」を品種改良した日本原産の栗です。
シバグリも木材として使用されています。
“桃栗3年柿8年”ということわざは“どのような事も成熟するにはそれ相応の月日がかかる”という意味で使われていますが、そこでも表現されているように栗は成長が早く、寿命は平均して50年前後といわれています。育つ環境によっては100年以上生き、中には樹齢800年ともいわれるほどの巨木も存在します。
辺材は灰白色、心材は黄褐色をしていて、年輪ははっきりとしています。
古くから木材としての優秀さを買われていた栗は、大量に伐採され栽培の量も減ってきたため蓄積量も少なく、近年では貴重な材となりつつあります。

栗の魅力
優れた耐久性
栗材は重硬で腐りにくく、水や湿気にも強いため保存性が極めて高いです。
そのため建物の土台や柱・家具などはもちろんのこと、鉄道線路の枕木にも使用されてきました。
縄文時代の集落跡である三内丸山遺跡では直径1mを超える木柱をはじめ、発掘された建物の主要部分にはほとんど栗材が使用されています。また世界遺産である白川郷・五箇山の合掌造りの主要部分にも栗材は使用されており、長い歴史の間雨風雪に耐え抜いてきたことからも、耐久性の高さを知ることができます。
国内産の材の中では最高レベルの強度を誇りますが、その反面加工や乾燥は容易とはいえません。
また木の中にはタンニンという成分が多く含まれており、防虫剤を使用しなくとも虫を防ぐことができるのも魅力です。

美しい木目
明瞭で力強い独特の木目をしています。木の風合いを感じる心地よい手触りも特徴的です。
黄色味を感じるその優しい色合いは、パイン材のように明るい色というよりかは少し落ち着きのある色の印象を受けます。栗の実を割った時の色と近いのでイメージしやすいかもしれません。
その美しい見た目と強度を活かしフローリング材としても大変人気があり、耐久性・耐水性に優れているので、フローリングには最適の木材なのです。
家具材としても使用される栗は、高級家具に用いられることが多いです。

経年変化を楽しめる
柔らかい色合いの栗材ですが、先ほど述べたタンニンという成分により黒っぽい色味へと変色し、木目の模様もくっきりとした輪郭を表しながら濃くなっていきます。
そうして使えば使い込むほど味が出て、しっとりとした艶やかな表情に変化していくのです。
徐々に自分の肌に馴染んでいく過程を楽しむことができるのも魅力の一つですね。

栗でつくられた家具のご紹介
栗を使ったアンティーク家具・ヴィンテージ家具
古来より人間の暮らしと深い繋がりのある栗は、アンティーク・ヴィンテージと呼ばれる時代にも活躍しています。
防虫効果という観点から、米沢箪笥・会津箪笥などの箪笥づくりによく用いられ、その他座卓・椅子・お盆・銭箱など様々なシーンでも重宝され、人々の生活に寄り添ってきました。
経年により深みの増した色合いへと変化したその姿は風情があり、存在感を際立たせます。
英語で栗は「チェスナット」といい、ヨーロッパでは細やかで美しい装飾や彫刻が施されたチェスナット材の家具がたくさん生まれ、現在でも大切に受け継がれ残っています。
イギリスよりもフランスで作られたものが多く見られます。

⇒ラフジュ工房の米沢箪笥の家具はこちら
⇒ラフジュ工房のヴィンテージ家具はこちら
栗を使った現代のブランド家具
現代人にとって栗は木材としてあまり馴染みがないかもしれませんが、栗材の家具は現代でもつくられ続けています。
栗材を使用した家具は、ナチュラルな色味と自然の雄大さを感じるダイナミックな木目により確かな存在感を放ち、その部屋全体を木の温もりで包んでくれるかのような力があります。
栗材にこだわって家具を作っている職人さんがいるほど魅力的な木材であり、後世にも受け継いでいきたい重要な銘木といえます。
どのような木も表皮に近い部分は規則性のない凸凹とした表面となっており、その自然味あふれる形状をそのまま活かした板のことを「耳付きの板」と呼びますが、栗材の家具でも見かけることが多々あります。栗は大径木が少ないため耳付きの大きな一枚板は希少性があり価値が高いとされています。また「ナラ」「オーク」のように耳の部分が腐りやすいということがないので、状態が良いまま安定して長く使用できる点も好まれる理由の一つです。
丈夫な材なので100年以上も前の古材をリメイクして使用することもあり、歴史を刻んだ味わい深い木目は非常に雰囲気があるため趣のある空間を作り出すことができます。