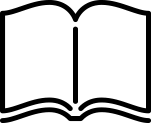ナラとはブナ科コナラ属の落葉広葉樹のことです。
ナラといえばどんぐりが実る木で有名で、公園や街路樹で見かけることも多く、日本人にとって昔から馴染み深い木ですよね。
何百年も生きるほどの生命力を持ち、お互いに助け合いながら純林を形成し、自らの力のみで森をつくり出すことができるため「森の王様」とも呼ばれています。
国内では本州・四国・九州と広い範囲にわたって分布しており、中でも北海道産のナラ材は大変良質で、その見た目や性質の良さから高級な木材として重宝されています。国外では中国、ロシアなどが産地として挙げられます。
ナラの木は英語でオークと呼ばれ、見た目も酷似していることからよく「ナラ=オーク」と間違われやすいですが、厳密にいうと両者は別物です。オークとは北米やヨーロッパに自生するナラに似た種類の木のことで、特にオーク材の中の「ホワイトオーク」という種類がナラ材によく似ていて、プロでも見分けるのが難しいほどです。
良質なナラ材は海外では「ジャパニーズ・オーク」と呼ばれ、大変な人気を博しています。
それでは、そんなナラについてもっと詳しく知り魅力に触れていきましょう!
ナラの種類
日本に自生するナラはミズナラ、コナラ、カシワ、クヌギ、ナラガシワ、アベマキの6種類があります。
ナラを木材として使用する際に呼ばれる「ナラ材」とは一般的に「ミズナラ」のことを指します。
ミズナラ
心材は淡褐色、辺材は淡黄色をしており、伐採の際に大量の水を噴出するためミズナラと言われるようになりました。
水分を多く含んでいるため燃えにくく、コナラやクヌギよりも寒冷な地を好んでいます。
樹高は大きいものだと35mに達し、別名「オオナラ」と呼ばれることも。
重硬で強度があり加工性や着色性にも優れているため、家具・建築・船舶・洋酒樽など幅広い用途に使われてきました。
国産のナラ材はヨーロッパなどに大量に輸出していた時期もありましたが、現在では大量伐採などが原因で数が減り入手困難な状況です。海外産のナラ材も輸出入の制限がかかったためさらに希少性が高まり、価格が高騰しています。

ナラの魅力
虎斑(とらふ)模様
見た目での最大の特徴は、虎斑と呼ばれる虎のような縦縞模様が柾目に現れていることです。
光に当たると銀色に輝いて見えるため、別名「シルバーグレイン」とも呼ばれています。
一見傷や凹みのように思われることもありますが、虎斑模様がある所は木が栄養を溜めていた部分であり、全てのナラ材に現れるわけではなく樹齢を重ねた天然木でないと現れないため、虎斑模様は選ばれた上質な木であることの証といえるのです。
独特な模様で存在感を際立たせるその美しい表情には根強い人気があり、著名な建築家フランク・ロイド・ライトもその魅力の虜になったそうです。

高い耐久性・耐水性
ナラ材に限らず広葉樹は硬く裂けにくい性質を持っているため、耐久性がとても高いです。
傷や凹みにも強いため、ぶつかったり、揺れたり、擦れたりと日常生活で常に影響を受け続ける家具や床などの材料によく使われています。
とても丈夫なので、子供に代々受け継ぐ家具としてピッタリの木材ですね。
またナラの木の中には道管を閉塞させるチロースという成分が含まれているため耐水性が高く、その液体を漏れにくくする特性を利用しウイスキーの熟成樽などにも使用されています。
木からは白檀(びゃくだん)や伽羅(きゃら)など線香でも使われるような香りもし、特にミズナラ樽で熟成されたウイスキーは高貴な香りをまとった逸品として、世界でも高く評価されています。
加えて、木に含まれた「タンニン」という成分により防虫効果も高く、水回りでも虫を寄せ付けません。

経年変化を楽しめる
ナラ材の家具は、ナチュラルで素朴な優しさを感じる美しい木目をしています。
板目にすると力強い山形の木目が現れ、柾目にすると流麗で真っ直ぐな木目の中に虎斑模様が存在感を光らせ、様々な表情で私たちを楽しませてくれます。
もともとはナチュラルな明るい色をしたナラ材ですが、長年使い込んでいくにつれ黄味は深さを増し、飴色へと変化していきます。
こうした経年変化を味わいながら、高い耐久性により長く使い続けることができるのも、ナラ材の大きな魅力のひとつですね。

ナラでつくられた家具のご紹介
ナラを使ったアンティーク家具
海外にとってのナラ材、つまりオーク材は欧米では古くから家具の木材として使用され、1500〜1600年代は「オークの時代」と呼ばれるほど主流でした。
その時代イギリスでは、チューダー家の紋章やゴシック様式のデザインを浮き彫りにした「チェダー様式」、バルボスレッグの華やかなデザインが特徴の「エリザベス様式」、ボビンターニングや挽物細工、リネンフォールドといった美しい装飾が魅力的な「ジャコビアン様式」と、様々なスタイルのオーク材家具が生み出されました。
その後1920年代イギリスでは害虫によってオークが不作となり、それを補うため開拓中だった北海道のナラ材が大量に輸出されることに。そのためこの頃のイギリスアンティーク家具では北海道産のナラ材が多く使われています。
ヒノキ・ケヤキ・スギなどが家具材の主流だった日本でも、この頃からようやくナラ材の魅力がわかり、家具材として使われていくようになります。


⇒ラフジュ工房のオークの家具はこちら
ナラを使ったヴィンテージ家具
ヴィンテージ市場においてもナラ材の家具は数多く存在しますが、海外のヴィンテージ家具で使用されているオーク材は基本的にホワイトオークであることが多いです。
イギリスヴィンテージ、北欧ヴィンテージ、和製ヴィンテージとそれぞれ個性は違えど、美しい木目やナチュラルな色味、素朴でありながら重厚な雰囲気も醸し出すナラ材は、クラシックにもモダンな空間にも合わせることができる万能な木材といえるでしょう。

⇒ラフジュ工房のヴィンテージ家具はこちら
ナラを使った現代のブランド家具
現代でも高級品として重宝されているナラ材の家具。
日本では松本民芸家具・永田良介商店・カリモク・神戸洋家具・北海道旭川家具・CONDE HOUSE(カンディハウス)など様々なブランド、メーカーでナラ材の家具がつくられ続けています。
無垢材の中でも非常に人気の高いナラ。木の素材そのものの質感や風合いをダイレクトに味わい、楽しむことができるのは無垢材の醍醐味ですね。
近年では国産のナラ材は希少で流通量も少ないため、北米産のホワイトオークが代替品として多く使われるようになっていきました。
時代と共にナラ材の在り方は変化してきましたが、これからも家具の世界では欠かせない重要な逸材として世界中で愛され続けることでしょう。

⇒ラフジュ工房の松本民芸家具の家具はこちら
⇒ラフジュ工房の永田良介商店の家具はこちら
⇒ラフジュ工房のカリモクの家具はこちら
⇒ラフジュ工房の神戸洋家具の家具はこちら
⇒ラフジュ工房の北海道旭川家具の家具はこちら
⇒ラフジュ工房のCONDE HOUSE(カンディハウス)の家具はこちら