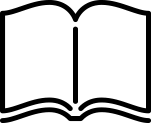帳場机(ちょうばづくえ)は、かつて商家の帳場(会計や帳簿管理を行う場所)で使われていた机です。商取引が盛んだった江戸時代から昭和初期にかけて広く使用され、店舗のカウンターや事務作業用のデスクとして重宝されました。
帳場机の特徴

帳場机は、幅広で安定感のある天板と頑丈な脚部、そして収納が備わっている点が特徴です。天板は帳簿や筆記用具を広げるために広く作られており、帳簿や書類などを整理するための引き出しや棚が備わっています。中には、貴重品を保管するための隠し引き出しが付いた帳場机も作られました。
また、時代ごとに装飾性が異なるのも特色です。例えば、明治期のものには細かな彫刻や装飾が施され、大正・昭和期のものにはよりシンプルで機能的なデザインが見られます。金品の管理が店の信用問題にもつながったため、帳場机の外観が店先の威厳やステータスにもつながっていました。そのため、帳場机の外観にも商家の格式や主人の趣味が反映されたのです。

帳場机の素材には、堅牢で長持ちする欅(けやき)や栗、杉などの木材が使われました。引き出しの取っ手や金具には、時代ごとの職人の技が反映されており、細部にまでこだわりが感じられます。
帳場机の歴史

帳場机は、商家が発展した江戸時代初期に登場し、昭和初期にかけて商家や旅館、問屋などで広く用いられました。
当時、店先で帳簿を広げて計算を行う場は「帳場」と呼ばれ、店主や番頭が座って金銭や取引の管理をしていました。
そこで使われた帳場机は、単なる作業用の机ではなく、店の運営を支える重要な家具でもあったのです。
簿記机の登場

帳場机は昭和初期ごろまで使用されていましたが、明治以降、西洋から洋家具文化や西洋式の簿記が伝わると、新たに「簿記机」と呼ばれる家具が登場しました。
簿記机は、事務作業用の机として銀行や企業で使用されていたもので、西洋では「ライティングビューロー」とも呼ばれます。机と収納の機能を一体化させたデザインが特徴です。
帳場机と簿記机は、どちらも帳簿をつけたり取引を管理するための机という点では共通しています。しかし、帳場机が商家での取引管理に使われていたのに対し、簿記机は企業や銀行などの事務作業向けとして利用されることが多かったと考えられます。
デザイン面では、帳場机に比べて洋風の要素が強く、シンプルで書類の整理がしやすい構造が特徴です。また、ライティングビューローのように扉を開くことで書き物スペースを拡張できるタイプも登場し、簿記机は次第に書斎やワークスペースの家具としても活用されるようになりました。
アンティーク帳場机の魅力

現在、帳場机が商家や店舗で使われることは少なくなってきましたが、アンティーク家具として人気を集めています。堅牢な作りや実用性、昔ながらのデザイン性などが注目を集める理由でしょう。
帳場机は木製で作られているため、和室はもちろん、洋室のインテリアにもなじみやすいのが魅力です。経年変化によって生まれる木の味わいや、使い込まれた跡が独特の風格を加え、ヴィンテージスタイルやレトロな雰囲気づくりにも向いています。
アンティーク帳場机のインテリア活用法
帳場机は、和の雰囲気を活かしながら、モダンな空間にも調和するデザインが魅力です。パソコンデスクや作業台として使用するほか、趣味の作業スペースやカウンター風の演出にも適しています。ヴィンテージの風合いを活かして、ショップのレジ台やディスプレイ台として使用する例も見られ、使い方次第でさまざまな表情を見せてくれる家具といえるでしょう。